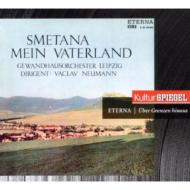全く脈絡ありませんが、「Victory at Sea」と言うのは1950年代に米NBC-TVで放映された、第二次世界大戦史の記録映画です。このサウンドトラックを担当したのがリチャード・ロジャーズですが、このCD以外には実はよく知りません。一定の年代以上のアメリカ人なら、たいていは見た記憶がある人気TVシリーズだったようです。「海での勝利」ですから、当然日本軍と戦ったミッドウェー海戦などが主題だと思います。NBC交響楽団により何曲か収録されている演奏は、さして面白くも印象に残るものもないのですが、タイトルに挙げた「ガダルカナル・マーチ」はなかなか軽快で勇壮で印象に残る演奏です。
なぜこんな曲を知ったかと言いますと、何年も前に観たオリヴァー・ストーンの映画「ニクソン」の中のワンシーンにこの曲が使われており、非常に印象に残っていたからです。オリヴァー・ストーンと言えば「プラトーン」や「JFK」など、数々のヒットを生み出したハリウッドの映画監督で日本でも人気ですが、一方非常に左寄りからのアプローチで米国近現代史についてもドキュメンタリーを制作しており、昨年NHKで放送されたのは記憶に新しいところです。保守層からは唾棄すべきアカ野郎と嫌われているようですが、本人自身は至って愛国心が強いと主張しています。
たしかに、ソ連との対立を避け、うまくバランスを取っていたルーズベルトが亡くなっていなければ、ひょっとしたら世界が東西に二分されることはなかったかも知れないし、日本に原爆が使用されなかったかも知れないと言われると、その後を襲ったトルーマンと言う保守体制のイエスマンの頭がいかに空っぽだったかと印象づけられます。ただ、ルーズベルト・JFK,=○、トルーマン・レーガン・ブッシュ=×、と言う単純な図式は少々荒っぽい印象も受けますし、彼独特の英雄像のつくり上げかたも鼻につくところも、無きにしも非ずと感じます。
そのストーン監督の1995年制作の映画「ニクソン」では、アンソニー・ホプキンスがリチャード・ニクソン大統領を演じ、二度の大統領選挙、ベトナム戦争やウォーターゲート事件を経て、側近に見放されての弾劾寸前での辞任に至るまでの息詰まる日々を描いています。当時の資料映像や音楽も随所にちりばめながら、政治ドラマながら観客をあきさせないエンターテイメントに仕上げていますが、その中のベトナム戦争で米空軍のB52爆撃機が、カンボジアを爆撃するシーンでこの「ガダルカナル・マーチ」が使われています。曲調は、スーザの行進曲「リバティ・ベル(自由の鐘)」とよく似た雰囲気の軽快なマーチです。参考までにそのスーザの「リバティ・ベル」を演奏したレナート・スラットキンの2004年のプロムス・ラストナイトコンサートの模様も付けておきます。モンティ・パイソンのギャグで6000人の聴衆を沸かせる冒頭の曲紹介も、なかなか芸があります。

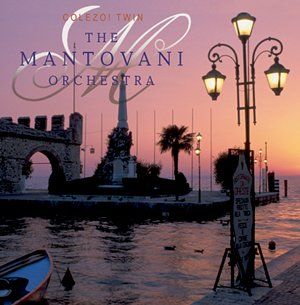


 「こんなのが欲しいな」と思っていたら、折よくTVショッピングでいいのを見かけ、即購入しました。自在脚タイプの「見台」、PCスタンドです。一見、歌舞伎や浄瑠璃の竹本でよく使われている「見台」のようなPC用スタンドで、両脚が自由に折りたためて、その間に自分の両脚や胴体がスポッと収まりますので、私のような「ながら」PC派に便利な代物です。高さが自由に調整出来るので、ベッドで寝そべっていても、ソファで寛いでいても、正座していても、ちょうどの高さにノートPCや本を置いて見る(読む、打つ)ことが出来ますので、本当に便利!デスクに置いたPCを長時間使っていると、結構首や肩に来ますし、視力調整がままならなくなって来た世代には、助かります(通販業者の回し者ではありません!)。ショップチャンネルで5千円くらいでした。(楽譜の譜面や、CDの解説も読めるので、一応「クラシック」のカテにしました。)
「こんなのが欲しいな」と思っていたら、折よくTVショッピングでいいのを見かけ、即購入しました。自在脚タイプの「見台」、PCスタンドです。一見、歌舞伎や浄瑠璃の竹本でよく使われている「見台」のようなPC用スタンドで、両脚が自由に折りたためて、その間に自分の両脚や胴体がスポッと収まりますので、私のような「ながら」PC派に便利な代物です。高さが自由に調整出来るので、ベッドで寝そべっていても、ソファで寛いでいても、正座していても、ちょうどの高さにノートPCや本を置いて見る(読む、打つ)ことが出来ますので、本当に便利!デスクに置いたPCを長時間使っていると、結構首や肩に来ますし、視力調整がままならなくなって来た世代には、助かります(通販業者の回し者ではありません!)。ショップチャンネルで5千円くらいでした。(楽譜の譜面や、CDの解説も読めるので、一応「クラシック」のカテにしました。)