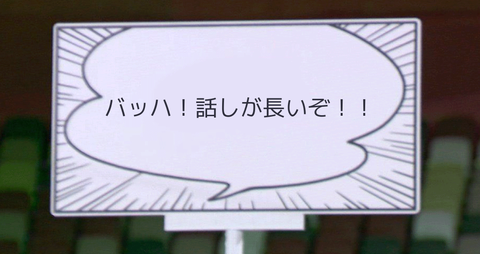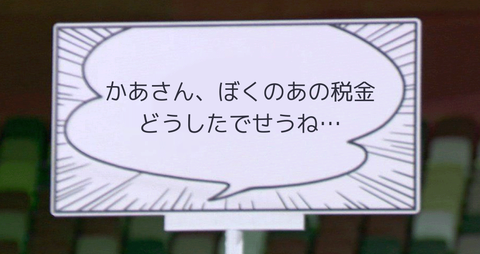沼尻竜典指揮東京フィルハーモニー演奏の「カルメン」、本日7月31日㈯の公演を観てきた。びわ湖でのオペラを観るのは、3月の「ローエングリン」以来で久しぶり。本公演は新国立劇場との提携公演で、東京ではすでに7月3日~19日の間に大野和士指揮で6回の上演が終わっている。演出は2年前にここびわ湖でも「トゥーランドット」(大野指揮、バルセロナ響)でなかなか面白い舞台をみせてくれたアレックス・オリエ。東京では現在再び新型コロナの感染者数が急増していて気になるところだが、かなり際どいタイミングでの引っ越し公演となる。なお、びわ湖での本公演は本日と明日の二回、ダブルキャストでの上演となるが、初日の本日の公演を鑑賞してきた。
「カルメン」と言えば数あるオペラのなかでも最もポピュラーな演目で、ストーリーもわかりやすく普遍的なテーマでもあるので、演出もオーソドックスなものから目新しいものまで、様々に料理されている。高齢客の多い日本ではどちらかと言うと無難でオーソドックスな演出が好まれるだろうけれども、せっかくアレックス・オリエの演出でそれでは、曲がない。なにかと言うと古典的な衣装や装置でないと文句を言う客も少なくないが、そういうものはわざわざ劇場に足を運ばなくても、DVDやブルーレイでいくらでも観れる。今回の上演は現代的な演出だが、なかなかに面白い上演だった。コロナ禍ということもあって後方は空席も目立ち、ざっと見た印象では8割ていどの客入りか。
まずはカルメンらが本来仕事をしている煙草工場は片鱗もなく、人気ロックミュージシャンの舞台セットということになっている。最初に幕が上がると、舞台正面全体にスチールのパイプで組まれた巨大な足場が設置されている。相当な量の鉄パイプが使われていて、やはりこれでもかと言う位に鉄骨を多用した、かつてのクプファーとシャベルノッホのコンビでよく観た舞台を彷彿とさせる(今回はピケ足場が大いに儲けているだろうw)。その前であばずれた感じのカルメン(谷口睦美)がひとり煙草に火を点けようとしているところにドン・ホセ(清水徹太郎)が通りかかって火を貸すところから始まる。ドン・ホセの部隊は軍隊ではなく、ロックコンサートの会場を警備する警察官らしい。普通のコンサートの警備に警察官というのは現実ではあまり考えられないが(過去のビートルズの公演など例外はあるが)、時節柄、五輪関連イベントの警備と脳内変換するとわかりやすい。まあ、そこはオペラだから、突っ込まない(笑)。部隊は制服の警察官たちと、それを指揮するスーツ姿の私服の警察官ということになっていて、モラレス(星野淳)やスニガ(松森治)、ドン・ホセはネクタイにスーツの私服警官ということになっている。警察がエライ国家ニッポンと言う意味だとしたら、いいセンを突いているかもしれない(笑)。
正面の巨大な鉄パイプの足場が上方に隠れると、舞台中央に2mほどの高さでプロレスのリングくらいの大きさのステージがしつらえられていて、ドラムセットを中央に、両脇にギターやベースに大きなアンプやマイクも設置されていて、なかなか本格的なロックのステージを再現している。カルメンはこのステージで、ロックのアイドルらしくハバネラを歌う。ここでカルメンが歌う真正面からのアップの映像がバックの大型モニターで映しだされるのだが、このアングルで撮影するには正面にカメラがないと撮れない映像で、その位置は舞台の正面か客席の前方の同じ高さでないと理屈があわないのだが、そこにそれらしいカメラは見あたらない。もしかしてホール最後方の調整室から撮るとすれば、相当なズームで撮らないとだめだと思うが… これはちょっと謎だった。またステージの上部にも巨大な鉄骨のフレームがしつらえられていて、なかなか予算がかかっていそうだ。まぁ、たまにはこういう面白いセットの「カルメン」があっても、いいではないか(笑)。砂川涼子のミカエラは、野暮ったいズボンに流行遅れのデニムのジャケットと、いかにも田舎から出て来た垢ぬけない格好をさせられていて気の毒だが、本来の役の意味をよく表現している。
上に書いたように「煙草工場」という気配はまったくないので、カルメンと喧嘩をおっ始めるマニュエリータはステージの準備をしていたローディーの女性と言った塩梅で、「煙がプカプカ」の合唱のところも、煙草の代わりにスマホのライトをゆらゆらと灯す、と言った感じ。二幕のリーリャス・パスティアの居酒屋は、特段どうと言うこともない、普通に酒場の雰囲気。「花の歌」を歌うドン・ホセは、バラを持っているのではなく、胸にバラのタットゥーをしているという趣向(フレディ・ハバードの「バラの刺青」を思い出した)。エスカミーリョ(森口賢二)の登場の場面も、闘牛士というよりロックスターといった感じ。三幕の密輸団のアジトは舞台上手に大きな化粧台と衣装ケースがあり、中央にも大きな機材ケースが二つあり、フラスキータ(佐藤路子)とメルセデス(森季子)がそこでタロット占いをする。とその前に、いかにもVシネマの極道コンビと言うイメージがぴったりのダンカイロ(迎肇聡)とレメンタード(山本康寛)が、いったいどんだけ大量にあるねん!? というくらい大量の怪し気な粉末のパッケージを、かばんからそのケースに次から次へと移し換えている。さすがにどこかの国の首相がお気に入りのパンケーキ屋さん、ってこともないだろうから、末端価格にすると軽く億単位になりそうで、ここは間違いなく笑うところだろう(笑)。四幕冒頭の闘牛場の外の場面は、舞台正面前方にレッドカーペットをズラッと敷いて、ファンたちが見守る前を、パンクロック風のアイドル(というより自分には吉本新喜劇の、ギャグはてんでおもろないけれども、いるだけで笑えてくるけったいな芸人の吉田ヒロにしか見えなかったがw)や、モデル風の女性、ポップスター、映画スターらしいのに混じって車椅子の男性らも登場し、舞台を下手から上手へ、また上手から下手へと颯爽と横切って行く。それはいいのだが、バックの群衆のコーラスが突っ立ってるだけで芸が無い。せっかく歌詞に色んな物売りとかが出てるんだから、もう少し手を加えればバラエティ豊かな場面になるのに。最後に嫉妬に狂ったドン・ホセがカルメンを刺殺する場面は、特段変わった仕掛けはなく、じゅうぶんに歌と音楽だけで観終わるという感じである。
以上はおもに舞台演出面から書いたが、何よりも今日は歌手が大変良かった。特にタイトルロールの谷口さんとドン・ホセの清水さんは、大変素晴らしかった!谷口さんは3月の「ローエングリン」のオルトルートで素晴らしい歌唱を聴かせてくれたが、今回のカルメンも素晴らしかった。清水徹太郎さんも、ここびわ湖ホールでワーグナーのオペラをはじめ、度々聴いてきたが、ドン・ホセのような主役級を聴くのは今回が初めてで、大変素晴らしい声量と情感豊かで安定した歌唱で、堂々たる歌いっぷりで大いに感動した。「カルメン」はいままで海外のプロダクションとキャストで何度も観てきているが、日本人歌手のドン・ホセで感動したのは、おそらく今回がはじめてかもしれない。
あと、トップバッターでモラレスを歌う星野さんも、冒頭から安定した歌いっぷりで声量もよく、じつに幸先のよい出だしを切ってくれた。最初のモラレスがしょぼいと、ガクッとすることも多々あるのだ。スニガの松森さんも、よく響く美しい低音で、いつものように素晴らしかった。エスカミーリョの森口さんは、最初ちょっと声が硬質かなと思ったが、ドン・ホセとの格闘以降よくなって行き、最後の闘牛士の姿は絵に描いたようで実に美しかった。上記したフラスキータ・メルセデス・ダンカイロ・レメンタードも、それぞれ個性が感じられる良い歌唱だったが、フランス語での早いパッセージが続く五重唱では、さすがにちょっと期待値のほうが大きかったかもしれない。ここは、うまい五重唱だととても印象に残る場面なのだ。コロナ対策の影響か、立ち位置の距離感が大きかったのが裏目に出たかもしれない(あんな早口だと、半端なくツバも飛ぶからな~)。とは言え、そこは贅沢な要求だ。合唱も全体的に距離を取っている印象があった。あとはもちろん、ミカエラの砂川さんも声量もよく、あいかわらずすごい人気ぶりだった。7年ほど前にここで「死の都」のマリー/マリエッタを聴いた時は、かなりリリカルに感じたものだが、その時に比べるとちょっと声が重くなってるのかな?と感じるところもあった。
沼尻竜典指揮・東京フィルハーモニーの演奏は、ダイナミックな聴かせどころとしっとりと美しい部分の対比が聴きごたえとしてはじゅうぶんだったが、所々、細部にやや仕上げの粗さを感じさせてしまう部分もなきにしも非ずで、これは会場の「慣れ」の部分もあるだろうから、明日の二日目はきっと良くなるのではないだろうか。
ところで、衣装はリュック・カステーイスというバルセロナのオリエ・チームの人のようだが、主役陣以外の衣装もこの人が担当しているとしたら、なかなか日本人の衣装のセンスを理解している人ではないかと感じられた。舞台美術は、やはりバルセロナのアルフォンス・フローレスで、ともに前回の「トゥーランドット」を担当している。大変見応えのある舞台と、聴きごたえのある素晴らしい「カルメン」だった。それにしても、こんなに良い公演でブラヴォーの声が掛けられないなんて、それだけが実に心残り!(バイロイトやザルツブルクみたく床キックでブラヴォーしたいんだけど、日本の会場のフロアは硬いからマネができないんだな、これが)

公演日時: 2021年7月31日(土)・8月1日(日)
指揮: 沼尻竜典 演出:アレックス・オリエ
出演(31日/1日):
<カルメン> 谷口睦美/山下牧子
<ドン・ホセ> 清水徹太郎*/村上敏明
<エスカミーリョ> 森口賢二/須藤慎吾
<ミカエラ> 砂川涼子/石橋栄実
<スニガ> 松森治*/大塚博章
<モラレス> 星野淳(両日)
<ダンカイロ> 迎肇聡*/成田博之
<レメンダード> 山本康寛*/升島唯博
<フラスキータ> 佐藤路子*/平井香織
<メルセデス>森 季子*/但馬由香
*...びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー
合唱: 新国立劇場合唱団、びわ湖ホール声楽アンサンブル
管弦楽: 東京フィルハーモニー交響楽団
↓新国立の記事。舞台写真が豊富。